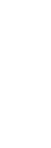from Staff
- 河合宏樹(兵士A 監督・撮影)
- 梅津和時(サックス・トランペット)
- ひらのりょう(舞台映像)
「兵士A」映像化に際して
2015年11月19日、私は映像の無力さをまたしても思い知らされてしまいました。
この1度きりの公演は、決して「映像では伝えることはできない」と、カメラを回しながらひしひしと感じていました。
私は公演後改めて、記録とは何かという自問をくりかえし、自分の活動の無意味さと戦うことになりました。
私がきちんとカメラを握り始めたのは、正確に言いますと2011年の震災以降になります。
そのとき、映画かぶれだった私にできることは、嫌というほど見させられた被災地の映像を撮るのではなく、起きてしまった事象に対して、自分の表現手段で真剣に向き合う人達の姿でした。
そして、無慈悲にも流れ去ってしまうものに対してそれをただただ記録していくということ。このようなアーカイブ活動をはじめ、多くの表現活動に触れてきたつもりです。
あの日も、私はいつものようにカメラを構え、一つの命を懸けた表現に対してひたすら向き合う意志で挑んでいたように思います。
公演後、お客さんからの大きな反響と、自分自身に生じた強い必然性から、7カメラ分、20時間に及ぶアーカイヴ映像と、もう一度真剣に向き合うことになりました。演者である旅人さん自身は映像作品化を逡巡していましたが、目撃者の一人として私はどうしてもこの公演を世に問いたかった。
真理を射抜くものこそ流れ去ってしまう不条理、それに抗いたかった。私はこの公演を決して無かったことにはさせたくないという使命感のもと、今後も続くだろう表現の歴史の中で、この作品を誰もが振り返ることができる、新しく触れることができる、そういった形で残したいと考えたのです。
記録映像は本公演と比べることはできません。その場にしかない臨場感というものは絶対的に存在します。
私は映像は別物になると考えています。私がファインダーを覗いて物語るその人間の光と闇に、その小さな可能性に、いつも懸けているつもりです。
それでいて、この大きなテーマと覚悟を背負ったライブの本質を一文字も間違いなく伝えなければならない葛藤と矛盾を抱えています(私は常にそうなのですが...)
この作品と向き合うには、自分が活動を始めた原点に立ち返り、ステージで行われていた事象というよりは、
七尾旅人、そして「兵士A」という人間に、いかに誠実に向き合えるか。また、その人間を見つめることが、必要でした。
結果、旅人さんが「兵士A」となり、一人で戦渦に飛び込み、その表現の葛藤と一人の人間としての矛盾の中でもがいている様子が自分の葛藤と矛盾にシンクしたときに、映像化への道すじが見えた気がしました。
七尾旅人の「兵士A」は、人を扇動したり、ある方向性に向けて合意を促し、安心させようとするものではなく、あくまで孤独な戦場だったということです。
もちろん観客を動員し、戦争や歴史が他人事ではないと誰もが考えたことでしょう。しかし、映像に時折映る人は皆、誰かと同調するわけでもなく、ただただ、自らに置き換えて、自らの心に問うていた。
画に映っているものは、歴史であれ、戦争であれ、原子力であれ、どんなに大きな問題であろうと、それはあくまで小さな小さな声が折り重なったものだった。
そういえば、旅人さんのうたはいつだって小さな声にもならない声を拾い集め、背負い、うたい続けていた。
そう考えたらこの作品の兵士Aくんは、七尾旅人の人生そのものといえるのかもしれない。
社会的なテーマを抱えたドキュメント映像にはイエスかノーかを必要以上に求める声が多いですが、
この映像のなかの彼の表情、咳、声の揺らぎ、涙に、鑑賞くださったすべての方が個々に受け取るものがあると私は思っています。
この兵士Aに誰でもなりえる未来がくるかもしれない
「兵士A、記録してくれていて本当によかった」そんな声を聴くたびに、これから何が起こるかわからない世の中で、当たり前だったもの、大切だった人、重要だった一線が、突然に損なわれるかもしれない。そして、そんなことすら気が付くと流れ去ってしまうだろうこの時代に、私はただただ、記録を回し続けたいと、強く思いました。
「兵士A」に寄せて
あの日、私は地縛霊になっていた。
地縛霊になってステージのソデの狭い空間で、じっと動かずに旅人の動きを見つめていた。
今までに経験した事の無い緊張が私を襲う。
もし地縛霊が常にあのような緊張を強いられて、じっとしていなければならないものだとしたら、
私は死んでも地縛霊にだけはなりたくない、と強く思った。
後半、ステージに登場してサックスを吹いたのだが、確かに力の限り思いっきり吹いた記憶があるのだが、
私は解放される事は無かった。
音楽というものはどんなものでも何かしら心地よいものなのだが、この日の音楽にはそれは無かった。
それが、たとえどんな暗い音楽を奏でたとしても。
音楽としては、悲しい物語でも過去のものなら嘆けばよい。泣けばよい。
しかし、これから現実になろうとする未来の悲劇にはまったく救いが無い。
しかも、その未来は過去から現在を通ってピンポイントでそこに流れ落ちようとしていることが、
旅人の歌や演奏や音響、そしてひらのりょうの映像を通して恐ろしいくらい伝わってくる。
「兵士A」
私は送られて来た映像を観てから、この文を書こうと思っていた。
だが、申し訳ないがまだ観ていない。
優れた作品である事は、あのライブの記録である以上、間違いない。
しかし、そこにかかわっていた当事者としては原稿の為になどといった理由では、まだ観たくないのだ。
この原稿を送ってからしっかりと覚悟を決めて、地縛霊ではなく一人の人間として、この映像と対峙したいと思う。
旅人さんから電話を貰った。『兵士A』という公演についての電話だった。
その通話はたしか三時間以上に及んだと思う。
映像演出という大役を任されてから、『兵士A』の物語は日に日にリアルになっていった。
長崎の被爆した祖父や、外国の海で戦死した栃木の大叔父のことを自然と思い出す。
旅人さんを追いかけるようにPCにかじりついて映像素材を作っていった。
自衛隊員の格好をした旅人さんを目の当たりにして、VJソフトを触る指が震えたのを
今でも思い出す。
あの現場で感じた身震いは確かに私のものだったけれど、
同時に旅人さんのものであり、観ている人々の
ものであり、未来の誰かのものだった。